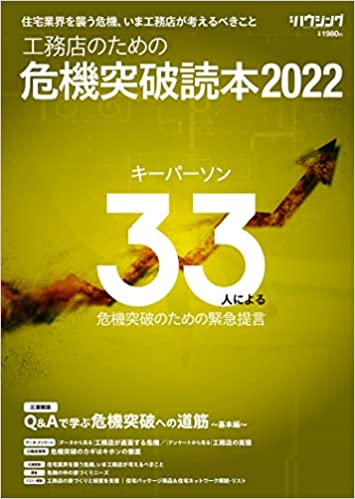『月刊地方財務』の連載企画「政策課題への一考察」の誌面に投稿する機会をいただき、「公共施設等総合管理計画10年の現状と地域に「負動産」を産まない公共施設FM」と題した論考を寄稿し、掲載されました。
公共施設の維持管理を現代の社会状況に適応させるための公共施設等総合管理計画は策定指示が出され10年が経とうとしていますが、数字的に見る進捗は捗っているとは言えず、それを進めるための公共FM(ファシリティマネジメント)に必要なことは何かについて私見を述べました。
公共施設・公共不動産の利活用の最適化、保有・活用の要不要に関する判断をどう進めるかはこれからの地域社会にとって重要課題だと考えます。こうした機会があれば、引き続き発信をしていきたいと思います。